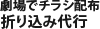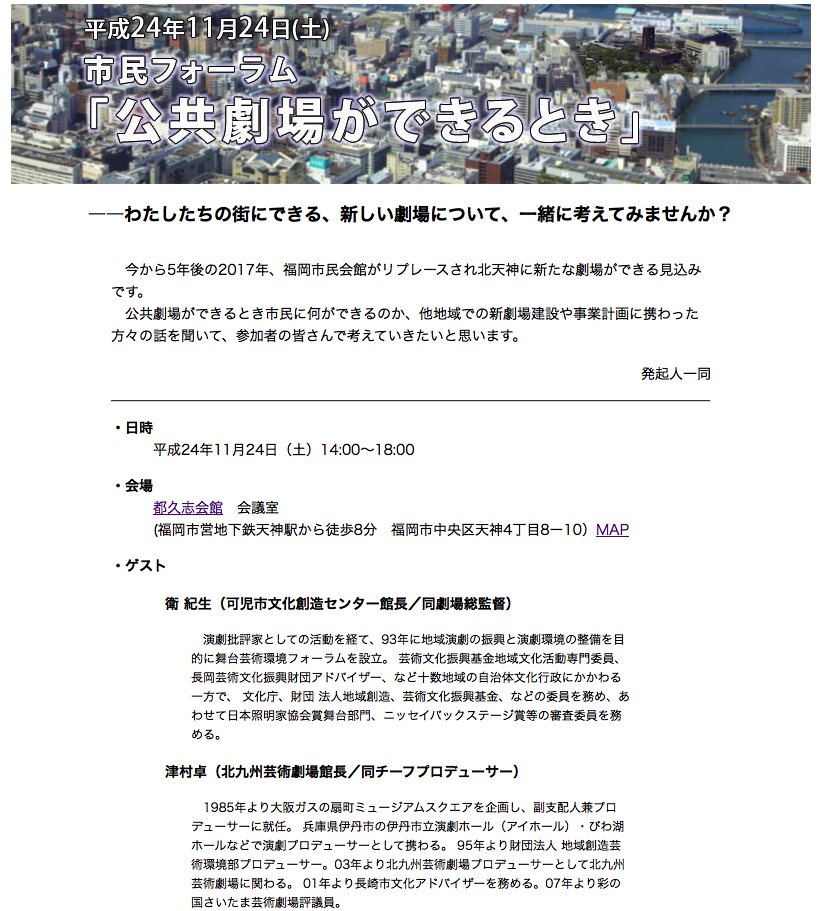![]()
制作ニュース
- PINstage高崎の「さくてきネクステージ from 福岡」Vol.8
-
12.11/13
高度成長期に国内で建設された公共ホールの多くが耐用年数を迎え、建て替えの時期に入ってきているようです。福岡でも1963年に建設された福岡市民会館が建て替えの時期を迎えています。
福岡から見ると、東京では毎年のように新しい劇場ができているような印象です。これは印象であって決して毎年のようにできているわけではないのでしょうが、東京以外の地域で、その地域に新たな劇場ができるということは非常にまれなことです。
福岡で本格的な小劇場ができるというのは20年、30年に1回あるかないかくらいのことだと思います。今後50年そういった劇場が新たに設置されないとしても不思議な事ではありません。福岡はまだいい方で、小劇場演劇に適した本格的な劇場がないという地域も少なくないでしょう。
東京であれば、多様な劇場があり、他の劇場といかに差別化するかということが重視されるように思います。一方、東京以外の地域では、新たにできる劇場が少ないことからより多様な要望が届き、一館でより多くのニーズをフォローする必要が求められます。必然的に多目的多機能の劇場を指向することになるでしょう。
劇場を利用する地域の芸術団体も、数十年に一度のハード建設へ様々な要望を上げていく傾向が強まるものと思います。
福岡では福岡市民会館の建て替えへ向けて、地域の演劇関係者を中心としたフォーラムが行われます。可児市文化創造センター館長の衛紀生さん、北九州芸術劇場館長の津村卓さんをゲストにお招きします。地元の演劇関係者の劇場への関心の高さの一端を伺うことができるといえるでしょう。
同じく九州で、平成25年にオープン予定のホルトホール大分では、地元の演劇人が自分たちの活動の場にあった客席数の小ホール設置の要望を行政に届け、その要望が実現したというように聞いています。
地域での新劇場の建設については以上のような状況があり、新たな劇場を建設する行政には、多様な意見のバランスを取ることが求められ、劇場の指針を決めるに当たり複雑な判断が要求されるということになるようです。
そういった要望をスルーして劇場を建設したとしても、地元の舞台芸術関係者と良好な関係を作れず、せっかくの劇場がその効用を十分に発揮できないということがはっきりしてきたと言えるでしょう。
このように、新たな劇場が建設されることがまれな地域においては、それだけに、多くの利害関係者の意見が入り混じり、複雑性を増していくという状況があると言えそうです。
地域の演劇関係者は劇場を利用する有力な利害関係者層です。その層とどのような距離感をとって劇場をつくるかが劇場設置者の腕の見せ所であり、1980年代以降に設置された公共ホールが多い日本の状況で、10年後以降に建て替えられる劇場にとって良い例を作っていくことが求められているように思います。

■高崎 大志(たかさき・たいし)■
地域演劇プロデューサー NPO法人FPAP事務局長 九州地域演劇協議会理事・事務局長
高校の時より演劇をはじめ大学演劇部をへて在学中に劇団旗あげ。役者・制作・照明・舞台監督を担当。
2003年NPO法人FPAP設立、事務局長。演劇公演企画やセミナー・ワークショップ等の地域演劇振興の自主事業の企画、地域演劇の劇評や、福岡・九州の演劇状況、国内の芸術環境格差に関するレポートなども手がける。
2008-10年(財)広島市文化財団 南区民文化センター主催「若手演劇制作者育成講座」講師。09年金沢市民芸術村「地域演劇制作者のための実践的制作講座」講師。2010年福岡・九州地域演劇祭の総合プロデューサー。
NPO法人FPAP:http://www.fpap.jp/
個人ブログ:http://sakuteki.exblog.jp/
twitter:@tahahahi
![]()