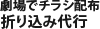![]()
制作ニュース
- 新長田で考える、ダンスをめぐる現場から(身体ごと投げだすかのように)/横堀ふみ vol.7
-
14.03/14


かなり遅れての第7号となり申し訳ありません。
今号は、これまでこのコラムでもご紹介致しましたように、ダンスボックスが新長田という地域の文脈となんらかの形で関わりながら、プロジェクトを行って来ていますが、これらのプロジェクトを進めるにあたっての個人的な背景や考えの経緯などを書き記したいと思います。
私が大学生時代はインドネシア学科に所属し、おもにバリ島の文化芸術/芸能を勉強しました。バリ島にも幾度か訪れ、ホームステイし、お祭りに参加させて頂く中で、芸能と生活とのあり方がとても豊かなものに見えました。日々のお供えも創造物のようなもので、日常の延長線上にダンスや音楽や歌や宗教があるかのように。踊ることや音楽を奏でることに誇りをもつ人々と多くであったからと言えるかもしれません。もちろん、短期滞在者から見えることはたかが知れていること、又バリ島の観光対象とも密接的に関わっていることもあることと思います。学生時代、様々な書籍等の資料にあたりました。その中で、大きく揺さぶられたのが、井上ひさし著の「宮沢賢治に聞く」(文芸春秋発行)でした。井上ひさし氏が架空の宮沢賢治と対談するという頁でのことでした。そこに、宮沢賢治は生前バリ島民の当時の暮らしについてよく知っていたのではないか、という問いかけがありました。「農民芸術概論」を執筆した宮沢賢治にとって、芸能と宗教と科学が結びついたバリ島民の暮らしは大きな影響を与えたものではないか、というようなテキストでした。宮沢賢治の「農民芸術概論」にここで始めて出会いました。
それから学生時代の最後のほうから、ダンスボックスに所属し、数々のダンス公演の制作に携わってきました。そして公演制作に追いつくことに必死だった約10年。やがて、機会も得て、アジアの各所でのリサーチや、国内外のフェスティバルの視察等、様々な地域での現場に訪問させて頂きました。その中で印象的だったことは、とくにクアラルンプールやマニラ、インドネシアの地域(ジャカルタ、ソロ、ジョグジャカルタ)、バンコクにおいて、その地域の文脈に密接に立脚したプログラムに立ちあう機会のあったことでした。作る者と見る者が共犯関係となることもあれば、政治や社会についての鋭い視点を投げかけることもあれば、自らのルーツについての思考することもあるような独特の匂いを発していました。当時、おもに日本におけるコンテンポラリーダンスの作品は、国や地域の枠組みを越えて、どの地域で上演してもあまり意味合いの変わらないものが多かった、つまり個人の事情や興味、アイデアに寄った作品が多く(その個人というものがその地域のある特徴を示すこともありますが)、関西の大阪で作られたものが東京で上演しようと福岡で上演しようとあまり意味合いは変わらず、もしかしたらバンコクやソウルで上演してもそう変わるものではないかもしれないという印象が強かったのです。表現が、その時代のその場の空気を照射しながら、まみえながら、立ちあがっていくのなら、もっとその場の磁場を吸い込んだ、批評性のある、独自の匂いを発する表現があってもいいのではないかと思い続けていました。そして、そのような表現をアーティストと共に立ち上げてみたいと考えていました。時は経て、2009年4月に新長田にダンスボックスが拠点を移した時に(もちろん数々の印象的な出来事を経て)、この新長田という地域でそのことに挑戦してみたいと考えました。


ここで、大学時代に感銘をうけてから、時々思い出すように読んでいた「農民芸術概論」がゆるやかに鮮明に立ち上がり始めました。そして、この思考/実践の軌跡に理念を与えた鶴見俊輔の「限界芸術論」(ちくま学芸文庫発行)へと辿りつきました。それは、芸術には三つの領域があるというものでした。
今日の用語法で「芸術」とよばれている作品を、「純粋芸術」(Pure Arts)とよびかえることとし、この純粋芸術にくらべると俗悪なもの、非芸術的なもの、ニセモノ芸術と考えられている作品を「大衆芸術」(Popular Arts)と呼ぶこととし、両者よりもさらに広大な領域で芸術と生活との境界線にあたる作品を「限界芸術」(Marginal Arts)と呼ぶことにしてみよう。
純粋芸術は、専門的芸術家によってつくられ、それぞれの専門種目の作品の系列にたいして親しみをもつ専門的享受者をもつ。大衆芸術は、これもまた専門的芸術家によってつくられはするが、制作過程はむしろ企業家と専門的芸術家の合作の形をとり、その享受者としては大衆をもつ。限界芸術は、非専門的芸術家によってつくられ。非専門的享受者によって享受される。
「限界芸術は、非専門的芸術家によってつくられ。非専門的享受者によって享受される。」こと、「両者(純粋芸術と大衆芸術)よりもさらに広大な領域で芸術と生活との境界線にあたる作品」について、新長田という地域で考察し、実践してきたい、またこれらの事象を「コンテンポラリーダンス」という言葉を使ってダンスや身体表現を行う行為と重なり合う面があるのではないかと考えました。もしくは、「限界芸術」というアイデアと、「コンテンポラリーダンス」というアイデアは意外と繋がらないように見えて、実はとても繋がる可能性を孕んでいるのではないかということ。そして、それらのこと考察することの中で、では、劇場におけるプログラムの必然とはなんだろうか、アーティストの役割はなんだろうか、作品ってなんだろうか、といった数々の問いかけが立ち上がってきます。これらの問いかけは、繰り返し・繰り返し、日々の中でループします。私が幸福であるのは、これらのループする問いかけを、試行し、実践することでのできる現場にいることです。
これらの実践の一つに「新長田のダンス事情」があります。昨年9月に5年目のイベントを行いました。踊ること、踊りを見せること、踊りを巡る様々なことについて、考察する機会となりました。そして、この2月、横浜で再演する機会をつくりました。これらの問いかけは、新長田という場所でしか成立しないのだろうか、新長田という地域だからこそ可能となった出会いを通して生まれた試行の数々はなにがしらの普遍性を持ちうるのか、それらのことを見つめる機会にできればと思いました。2014年3月4日現在、横浜公演はぶじに終えることができました。次号ではそのご報告もできればと思います。

写真:倉科直弘
■横堀 ふみ(よこぼり・ふみ)■
NPO法人 DANCE BOX プログラム・ディレクター/制作
平成18年度文化庁新進芸術家国内研修制度研修員。平成20年度ACC(Asia Cultural Council)のグラントを得て、約6ヶ月間にわたり、アジア6カ国とNYにおいて舞台芸術の実態調査を実施。おもにアジア間におけるネットワークの構築を目指し、レジデンス・スペースや劇場、フェスティバルのディレクターらとの交流促進を行っている。
![]()