![]()
制作ニュース
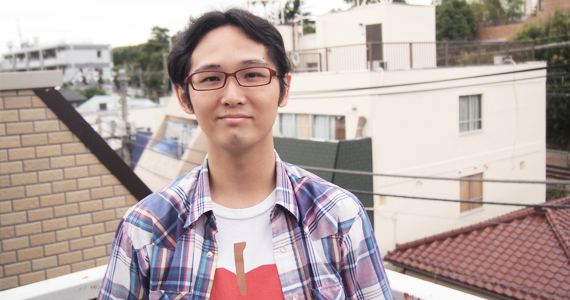
第一線で活躍する制作者に、これまでの道のりと仕事観を尋ねる「シリーズ“制作者のキャリア”」。今回のゲストは、こまばアゴラ劇場職員であり、劇団「青年団」の制作部でもある木元太郎。劇作家、演出家、俳優、そして制作者。あらゆる部門で現代小劇場界をリードする才能を輩出し続ける演劇集団の中で、濃密なキャリアを積んできた期待の若手制作者が語る、仕事へのこだわり、そして、悩みとは?
周りを見渡せば必ず面白いものがある

――演劇との最初の出会いはいつ頃ですか?
高校に入学して最初に話しかけた友達のグループに演劇をやっている人がいて、高校の演劇部に入っていたんですね。彼らといっしょに行動していく中で自然に演劇部の手伝いをしていて、3年生の時に正式に入部しました。福岡でやっている小劇場の公演にもよく連れて行ってもらいました。
――卒業後も演劇を続けていこうと思っていたんですか?
もともと絵を描くのが好きで、演劇部と並行して美術系の予備校に通っていたんです。で、3年の時に受験どうしようかなって考えて美大のパンフレットを見ていたら、多摩美(多摩美術大学)に「映像演劇学科」っていう謎の学科があることを発見して(笑)。他の油絵の学科は落ちたんですけど、そこだけ受かったんです。ただ、今改めて考えると、受験で上京してきた時、試験と試験の合間に下北沢に行って芝居を観たりしてたぐらいなので、油絵の学科に受かっていたとしても何らかの形で演劇に関わっていたとは思いますね。多摩美の演劇コースは当時、清水邦夫さんが教授で、各自が学内で作品作りをしていくんですけど、1つ上の学年に、その後「小指値(現・快快)」として活動していくメンバーがいて、彼らともいっしょに作品を作っていました。
――「小指値」には旗揚げから参加したんですか?
「小指値」の旗揚げ公演は大学の卒業公演だったんですけど、基本的にはその学年のメンバーが中心に製作する形なので、学年の違う僕は横でその様子を見ていただけですね。
――「制作」という仕事にはいつごろから関わりだしたんでしょうか?
年に2本ぐらい学内で作品を作る機会があって、最初は自分で作・演出したり、出演したりしていたんですけど、3年生のときに、これまでとは違う形で何かやりたいなと思い立って、パンフレット等を作る仕事に回ったんです。福岡にいた頃に観ていた「あなピグモ捕獲団」という劇団があるんですけど、その劇団のカラーというか、公演ごとに左右されない部分のデザインが高校生の僕にとって憧れで印象に残っていて、そういうブランディングみたいなものに興味があったんですね。で、見様見真似で当日パンフレットや掲示物などを作ったのが、制作的な仕事をした最初だったと記憶しています。当時のパンフレットに「制作」とクレジットしていたかは定かじゃないですが。それから、それと同時期に小指値のメンバーから「CINRAマガジンというカルチャーメディアが新たに演劇のジャンルを紹介することになって演劇に明るい人を探している」ということでご紹介をいただいて、ほぼボランティアみたいな感じだったんですけど、そこで自分の好きな劇団を紹介するライターの仕事をさせてもらうようになりました。多分その辺りから、「面白いものを自分で作り出そう」という感覚から、「周りを見渡せば必ず面白いものがある」という方向に自分の中で興味が変わっていったんじゃないかと思います。
――興味の対象がそれまでと微妙に変わってきて、辿り着いたのが「制作」だったと。
CINRAと小指値の活動を並行して続けていたんですけど、当時は「制作」というもが何なのか自分ではよく分かっていなかったと思います。そもそも小指値というカンパニーが、明確に役割分担をせずにその時々で各自のやれることで作品に関わっていく、というようなスタイルでしたから、演出からの指示で急に舞台に出演することもありましたし、音響のオペレーターをやったりもしましたし、特に「自分は制作だ」という意識もなかったかと思います。
――なるほど。一般的な「劇団制作=事務方」とは違う感覚、クリエーションの一部として無意識のうちに制作的な仕事をマルチにやっていたんですね。小指値を辞めたのは?
自分自身の卒業制作に取り掛かるようになってから、次第に小指値の活動から距離を置くようになっていきました。その理由は、年齢が他のメンバーより下だったこともあると思うんですけど、カンパニーに自分が振り回されることが多くて(笑)。直接のきっかけになった出来事が何かあったわけじゃないんですけど、例えば、彼らは会議の中で「解散する」とか「辞める」っていう話を持ち出すことが多かったんですね。だから、たぶんどこかで「そんな解散、解散って言ってる人たちとはずっとは続けていけないな」と思っていたんだと思います。その後の彼らの活躍は皆さんご存知の通りですが(笑)。
![]()










