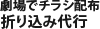![]()
Next舞台制作塾
|
こんな方に向けた講座です |
日本国内外の舞台芸術・舞台制作の状況を学びたい制作者・ドラマトゥルク・アーティストの方 |
|
舞台制作の実務で使う英語コミュニケーション能力を向上させたい方 |
※受講に関しての英語力のレベルは問いませんが、本講座ではアーティストやカンパニーの活動紹介テキストを英文で予習するなど、初歩的な英語能力を前提としたプログラムを実施する予定です。予めご承知置きください。
※本講座の英語表現プログラムは、英会話全般のスキル向上を目的とするものではなく、舞台芸術の現場で知っておきたい部分に特化した内容となります。
いま日本で舞台芸術活動を行う私たちにとっての「国外と国内」を考えるための、思想や知識の習得と英語の実践を組み合わせた、全10回のゼミが開講します。
各回の講義は、3本の柱で構成されます。
1. 劇場とフェスティバルを支柱として、国際的な舞台芸術の枠組みを知る
2. 国際的に活躍するプロデューサーやドラマトゥルクの仕事をもとに、これからの舞台制作者像を考える
3. 舞台芸術・制作に特化した英語表現を学び、日本国外の人とのコミュニケーションスキルを向上する
講師は演出家・ドラマトゥルク・翻訳家として活躍する岸本佳子さん。また、国内外で活躍する様々なゲストを迎え、対話をしていきます。
プロフィール

岸本佳子(きしもと かこ)
演出家・ドラマトゥルク・翻訳家
2009年より多国籍・多言語劇団「空(utsubo)」主宰。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。米国コロンビア大学芸術大学院(MFA)ドラマツルギー専攻。翻訳に、ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマ『ライフ・アンド・タイムズ – エピソード1』(静岡県舞台芸術センターSPAC主催)、ロジェ・ベルナット作『パブリック・ドメイン』(フェスティバル/トーキョー)等。東京大学・専修大学非常勤講師。芸創connect vol.7にて最優秀賞受賞(演出)。
講師からのメッセージ
せっかくなので、例えば実際にどこかの国に作品を持って行く時、あるいは国内で海外ゲストへの対応を迫られた時などに使える英語表現等を確認しつつ、劇場やフェスティバルといった枠組み自体やその中身について知り、さらに、今ひとつ現在の日本の演劇事情に追いついていない「制作」という単語に、いまだ醸し出されていない新たな風味を付加していくためのヒントが詰まった講座になると良いなと思っています。そのためのキーワードの一つとして、ドラマトゥルクという仕事に着目しようという魂胆です。(岸本佳子)
カリキュラム
| 日時・カリキュラム |
|---|
| ① 2/24(火)19:00-21:30
イントロダクション(海外のフェスティバル基本情報集) 海外のフェスティバル基本情報集 アヴィニョン、エジンバラ、ベルリン、クンステン、ボム、シビウ、スポレートetc. 名だたる国際演劇フェスティバルについての網羅的な解説と共に、次週からお迎えするゲストとの議論をより濃密にするため、数々のフェスティバルの中から主要なものを取り上げ、その現状と課題を探ります。英語塾①:自己&他己紹介とEメールの基本 日本の学校で英語の授業を受けて来た中で、基礎英会話、Eメール等に必要な文法や単語は充分勉強できている、ハズ。でも、いざとなると英語がなかなか口をついて出てこない。 そこで必要なのは、頭の中で眠っている単語や文法の固まりの中から、必要な場面で必要な所だけを引き出すためのとっかかりです。なので、制作ゼミ英語パートは、この「知っている」と「実際に使う」との間をつなぐヒントを提供する内容を目指します。第一回は、英語での自己紹介&他己紹介と、Eメールの書き方の基本を確認します。 |
|
② 3/3(火)19:00-21:30 「外からの視点」と「内側からの視点」 ゲスト:ウルリケ・クラウトハイム(舞台芸術コーディネーター) ドイツと日本 フェスティバル/トーキョーやドイツの劇場で制作・コーディネーターのお仕事をされてきたドイツ出身のウルリケ・クラウトハイムさんをゲストに迎え、これまでのお仕事内容をご紹介頂くと共に、各フェスティバルのコンセプトやディレクターによるオープニングスピーチを比較することで、それぞれの公演プログラムの違いや類似点について考えます。英語塾② 前回の自己&他己紹介に引き続き、もう少し詳しくご自身の活動や専門分野について話す、あるいは相手に質問をして情報を引き出すための定型文を学びます。また、先週から発展して、演劇制作に特化した内容のEメールのサンプルを参照します。 |
| ③ 3/10(火)19:00-21:30
「都市」と「観客」 ゲスト:李丞孝[イ・スンヒョウ](フェスティバル・ボム ディレクター) 韓国と日本 2014年よりフェスティバル・ボムのディレクターを務めるイ・スンヒョウさんをゲストに迎え、異なる都市でフェスティバルを同時開催することで、作品ではなく観客が移動するという、独特のディレクションに至った思考の足跡をお話いただきます。英語塾③ 英会話と英文Eメールの発展編に加え、リミニ・プロトコル、フォースド・エンタテインメント、グリーンピグといった、国際的に活躍する様々な劇団の英文ステートメントを読みます。初見で読むのが難しい場合は、事前に予習のための資料をお渡しします。 |
| ④ 3/17(火)19:00-21:30
「フェスティバル」と「社会」ゲスト:植松侑子(Explat理事長) フェスティバルという大きな枠組みに対し、現実に運営を行なう舞台制作者の実際のお仕事はどのようなものなのか、フェスティバル/トーキョーをはじめとする数々の現場で制作者として活躍してこられた植松侑子さんをゲストとしてお迎えし、お話を伺います。 |
| 英語塾④
前回までの英会話を復習しつつ、新たな定型文を学ぶことで会話の幅を広げます。後半は、ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマとチェルフィッチュの劇団紹介文と、両劇団に関する批評などを読みます。 |
| ⑤ 3/24(火)19:00-21:30
「フェスティバル」と「社会」② 初回から前回までの内容をふまえつつ、フェスティバルとは何か、についてディスカッションをします。ドイツや韓国と日本ではどのあたりの事情が異なっているのか、他国の事例から取り入れられるものは何か、逆に輸出し得るものは何か、等、フェスティバルをめぐるテーマのまとめをしたいと思います。英語塾⑤ 前回までの英会話を復習しつつ、新たな定型文を学ぶことで会話の幅を広げます。後半は、アリアーヌ・ムヌーシュキン率いる太陽劇団の劇団紹介文と、その作品に関する批評などを読みます。 |
| ⑥ 3/31(火)19:00-21:30
劇場システムの各国比較 国立劇場 / 小劇場 / 公立劇場 フェスティバルという一時的な都市の祝祭に対し、劇場は1年を通して一貫したプログラムを提供する固定された「場」です。日本でも大きな反響を呼んだ劇場法の議論などもふまえつつ、劇場というシステムについて、様々な国との比較から日本独特の課題や問題点を探ります。英語塾⑥ 新たな定型文を学んでいくと、やや困難な熟語や慣用句にも出会わざるを得ません。それらの中で、劇場や劇団、作品などについて話す上で特に使えるものをピックアップして学びます。後半は、オン・ケンセン率いるシアター・ワークスの劇団紹介文と、その作品に関する批評などを読みます。 |
| ⑦ 4/7(火)19:00-21:30
「媒介すること」と「プラットフォームを創ること」 ゲスト:山口真樹子 アートマネジメントという単語がまだ日本に定着する以前から、現場で経験を培って来られた山口真樹子さんをゲストにお迎えし、国境をこえて人と人とを繋ぐための「場」をつくること、についてお話しいただきます。英語塾⑦ 前回までの英会話を復習しつつ、新たな定型文・熟語・慣用句を学ぶことで会話の幅を広げます。後半は、ピナ・バウシュ、ケースマイケル、マリー・シュイナールといった振付家の紹介文や作品の批評を読みます。 |
| ⑧ 4/14(火)19:00-21:30
ミュージカルとドラマトゥルク ゲスト:小嶋麻倫子(東宝株式会社 演劇部 プロデューサー) コロンビア大学大学院でドラマツルギーを専攻後、シアタークリエや帝国劇場でプロデューサーとして様々なミュージカルを手がける小嶋麻倫子さんをゲストにお迎えし、これまでのお仕事や今取り組んでいらっしゃるプロジェクトについてお話しいただきます。英語塾⑧ 前回までの英会話を復習しつつ、新たな定型文・熟語・慣用句を学ぶことで会話の幅を広げます。後半は、ブロードウェイ・ミュージカル『Matilda』と『Once』の紹介文と、両作品に関する批評などを読みます。 |
| ⑨ 4/21(火)19:00-21:30
協働へのヒント 近年、アートで地域を活性化する、を合い言葉にさまざまな土地でさまざまな芸術祭が開催される一方で、作品の批評性と地域とのつながりをどう両立させるかなど、課題も徐々に浮き彫りになりつつあります。各地で展開するアートプロジェクトの成功例や問題点を参照しつつ、他者と協働すること、について考えます。英語塾⑨ 前回までの英会話を復習しつつ、新たな定型文・熟語・慣用句を学ぶことで会話の幅を広げます。ウィリアム・フォーサイスとダムタイプの紹介文と、両作品に関する批評などを読みます。 |
| ⑩ 4/28(火)19:00-21:30
どこからどこまでが「制作」? 英語のトレーニングを個人的に続けていく上で役に立つ、主にオンライン上のフリー・リソースをご紹介します。 |
募集概要
| 講料 | 通し受講…21,600円(税込)
※単発受講…1回につき2,700円(税込) (空席がある場合に限り、随時募集いたします。) |
|---|---|
| フォロー
制度 |
[通し受講の方のみ]
欠席した回の映像視聴が可能です。 ※映像データの貸出はしておりません。Nextミーティングルームでの視聴となります |
| 定員 | 通し受講…30名 |
| 会場 | Nextミーティングルーム(東京都江東区亀戸7-43-5 小林ビル 2F) |
| 申し込み
問合せ |
※受付は終了しました。
有限会社ネビュラエクストラサポート Next舞台制作塾事務局 TEL.03-5628-1325 e-mail Next@next-nevula.co.jp |
提携:豊島区立舞台芸術交流センター あうるすぽっと/NPO法人アートネットワーク・ジャパン
助成:

アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)
2015年05月25日 終了講座
![]()