![]()
制作ニュース
- 「制作のスパイス」第2回:会田 大也さん(東京大学大学院 特任助教)
-
14.11/18
制作者にとって直接、気づきやキャリアのヒントになるような話でなくても、料理の味付けがスパイスによって変わるように仕事の味付けが変わるような何かがあるかもしれません。そんな要素を、Next企画営業部の川口聡の視点で探ってみました。
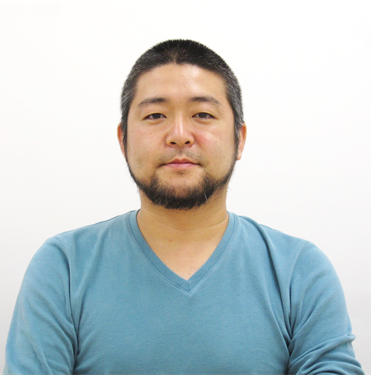
第2回:会田 大也さん
(東京大学大学院 特任助教)
東京大学大学院ソーシャルICTグローバル・クリエイティブ・リーダー[GCL]育成プログラム特任助教。2003年開館当初より11年間、山口情報芸術センター[YCAM]の教育普及担当として、メディアリテラシー教育と美術教育の領域を横断する形で、オリジナルのワークショップや教育コンテンツの開発と実施を担当する。一連のワークショップは、第6回キッズデザイン大賞を受賞。担当企画展示「コロガルパビリオン」が、第17回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品、一連の「コロガル」シリーズが2014年度グッドデザイン賞を受賞。
2013年、国際交流基金主催の日・ASEAN友好40周年事業である、国際巡回メディアアート展「MEDIA/ART KITCHEN」キュレーターに選出。
会田大也さんとは、舞台芸術制作者オープンネットワーク[ON-PAM]の地域協働委員会が企画・実施した山口県山口市での委員会で初めてお会いしました。このインタビューは山口市で会田さんが仲間と作られたアートセンター「Maemachi Art Center[Mac]」で伺ったお話と、後日、東京でお会いして伺ったお話とを、再構成してまとめています。
伺ったお話は、会田さんのキャリアにおけるアートとの関わり、2013年までの11年間、「教育普及」担当として在籍して活動された山口情報芸術センター[YCAM]でどういうワークショップ(以下、WS)を行なってきたのかや、企画展示した「コロガル公園」(2012年・YCAM)や「コロガルパビリオン」(2014年・YCAM)について。美術館の教育普及担当であるにも関わらず子供向け遊具をなぜ作ったのかについて、会田さんのWS観などから“創造性な価値を生み出す発想”を探ってみたいと思います。
 |
 |
| 山口情報芸術センター[YCAM] | |
さっそくですが東京ではどういうお仕事をされているのですか?
東京大学の大学院にて特任助教として勤務しています。次世代のリーダーを育成するコースで大学院生向けにWSの方法論を教えています。大学院生も今、社会的な課題を扱う研究が増えており、たとえば計算機とかITのコンピュータ科学の分野を研究していても、性能そのものを競うというようなことだけではなくて、それが社会の中でどう使われるのか、具体的な利用状況を踏まえてコンピュータについて研究するという分野も活発になってきています。
現代においては、医療、経済、人文科学も含め、専門の学問というのがいかに実際に社会に生きている人と関わるのか、を含めて研究している人も増えてきているのですが、WS的な手法・アクションリサーチの手法などを知らないままこれらの研究に突入するため、実際に人と接するコミュニケーションの作法とか、話の仕方とかほとんどわからないまま対人的なリサーチを行わざるを得ない。すると、入手できるデータの精度にばらつきが出てしまうこともあり得る。社会と関連する研究としての精度を求めていくときに、WSファシリテーションのスキルが求められる、という状況が生まれてきています。
会田さんのキャリアについて聞かせて下さい。どういう形からアートの世界に入られたのですか?
僕はまずはじめ、東京造形大学という美術大学で現代美術に触れました。現代美術は、絵画や彫刻のように、手技としての技術がないと作品を生み出せない世界とは異なり、レディメイドで・・・すでにあるものの組み合わせみたいなもので作品が作れる・・・ということを知って、「あ、これなら僕にもできる」というふうに安易に思った・・・というか、勘違いからスタートしたんです(笑)。
そのときの先生が「社会に出た時にはいずれにしても社会人として振る舞わなければならないんだから、学生のうちはアーティスト気取りでもいいんじゃないか」ということを言っていたので、僕も素直に先生の意見を聞いて作品制作とか発表とか、いわゆるアーティスト気取りなことをしていました。
そもそもはアーティストになろうとしていたのですか?
アーティストが職業だとは思っていなかったので、目標としてアーティストになるというのはピンと来てなかったですね。むしろ作品が売れていくということはどういうことなのか、ということを考えていました。それと今でこそ当たり前なんですけど、当時は美術館やギャラリーのみで作品が鑑賞されていることに違和感を覚えて、町の中に作品を鑑賞できる場を作ることそのものに興味を抱き、下高井戸の駅の周辺で「ブランクハンティング」という空き店舗を使った現代美術の展覧会を作ったりしていました。
町の中に作品を置くという活動は、当時、他の場所でも行われていたのですか?
たとえば、福岡県の博多天神の「ミュージアム・シティ・天神」(1990年~)という企画では百貨店の中にどんどん作品を置いていくというようなことが行われました。また、「水の波紋」(1995年)という展覧会が東京で行われ、町全体をアートのフィールドとして捉えていくということが行われました。日本でもそういう動きが起こりはじめていた時代でした。明確な理屈はありませんでしたが、「そうすることが正しいんだ」という革新性はなぜか感じていましたね。おこがましいですが、ギャラリーの中だけでやることは、つまらないとさえ思っていました。
大学卒業以降はどういう道に進まれたのですか?
大学を卒業したあとは、もう少し自分の学んでいることを究めたいと思い、岐阜県立の情報科学芸術大学院大学(IAMAS)というメディアアートの学校に3年間通いました。メディアというものが登場して以降、人のコミュニケーションというものがどういうふうに変わったかということを考えるメディア美学というコースです。サイバネティクスとかインターネットというものが、人の哲学や思想にどういう影響を与えたのかということを学んでいましたが、僕はあんまりアカデミックなことはやっていなくて。そこでも展覧会を作ったりしていました。ただ、身の回りにはテクノロジーと表現についてのトライアルを繰り返す友人がたくさんいましたので、それらのことについてじっくり考えることができる時間でした。
美術をコミュニケーションやメディアというものと結びつくフィールドで考えてこられたのですね。
そうですね。今思えばそこまで意識していなかったのですが。少なくとも歴史上、美術家と言われるような人たちは、どの時代においても当時の最先端の技術を使っていたはずなんです。
絵の具が持ち運び可能なチューブに入った形になったときに、外に出て絵の具で絵を描くことができるようになった。写真が生まれたときに、それまでにない新しい視覚の表現が出てきた。映画もやっぱりその当時において新たな芸術性が追求されてきた。歴史的に考えてみれば、芸術というのは常に最先端の技術や最先端のメディアと離れることはないと思うんですね。その流れでいくと現代において、アートのことを考えていくときに、電子テクノロジーとかネットワークについて意識しないのはおかしい・・・というか当然だと思っていました。
お話を伺っていると2003年に、山口情報芸術センター[YCAM]に行かれたのは必然だったという感じがしますね。
YCAMへは、元IAMASにいた助手の方が1年前に山口に移りスタッフとして働いていたので、声を掛けてもらって採用試験を受けにいったという経緯ですね。
会田さんはYCAMに入られたときから「教育普及」担当だったのですか?
そうです。僕は「教育普及」専任でした。YCAMとしては「教育普及」に力を入れていくということで、スタッフも充実していました。
YCAMは教育普及活動に対する投資は大きかったです。年間数百万の予算が教育普及プログラムへ割り当てられていたし、展示や舞台公演といったコンテンツと同格の位置づけとして教育普及を位置づけていたのは、画期的だったと思います。
YCAMで、「教育普及」部門の担当になられたというのは、当時はどういう心境だったのですか?
地域と一緒に何かをやっていくということは学生時代から行なっていたことでもあったので、必要なこととして理解はできましたね。ただ、「教育普及」とはどういう仕事で、全国的にはどんな活動があるのかはまったく知らなかったし、美術館でWSなどをやっていても、僕はまったく参加しないタイプだったので(笑)、そういうことが好きなわけでもないし、という比較的冷静な感じでした。
YCAMに就職する前はWSをやったことがなかったんですか?
はい。むしろ疑っていました。WSが表現やコミュニケーションだと思っていなかったというか(笑)。
(笑)
ワークショップを行うよりも作品を制作することの方が重要だと思っていました。ワークショップというのはフワフワしたものであり、善し悪しの評価がしづらい。それは今でも変わらないのですが、いずれにしても当時、WSとかごまかせるような要素が多いところでは戦いたくないと思っていました。
一般的に美術館の「教育普及」というのは、どういう位置づけなのですか?
普通の美術館の形態でいうと学芸員(キューレーター)というのが花形の仕事で、若手の新人が任されるのが「教育普及」という形態が多いなと思います。でも、僕が働いていた10年の間にだんだんそれが変わってきているように思います。YCAMの場合は、10年前はメディアアートっていう言葉自体が地元に馴染みがなかったし、YCAMの建設が市長選の争点になったこともあり、必要性を納得してもらうというミッションもありました。と言いつつも、今考えればその流れが必然のように見えますが、当時は別にそんなに戦略的に動いていたわけでない、というのが実情ですね(笑)。目の前のことを懸命にやっていた、という方が実態に即しています。
YCAMが立ち上がった際は、「教育普及」部門は他の美術館で行われてる形態の「教育普及」を実施するという意識だったんですか?
まったくそうではなかったですね。就任してからそれなりにリサーチはしてみたんです。他のWSを見に行ったり、キーマンになる人のお話を聞きにいったりしました。子供の集中力がどういうときに切れるかとか、ちょっとしたことで子供は興味をなくしてしまうんだなとか、子供たちの様子を細かく見ていたという感じですね。
大人が最初にレールを敷くのに一生懸命で、子供たちは行きたくもないレールをいやいやながらついてくみたいなWSとかをいくつか散見して、「本当に参加者に有意義なプログラムって何だろう?」ということを考えるようになりました。
YCAMとしても「教育普及」の設計は会田さんに一任していたのですか?
オープン直後は他の皆さんも忙しく、それぞれ自分の持ち場だけで手一杯なので他担当者の仕事を細かくチェックしている暇がなかったというのが実情でした。僕自身も他の事業の撮影補助とかアーカイブとかをやっていましたし、いろんな人がマルチな能力で、YCAMのさまざまな事業を形にしていました。
会田さんのメインのお仕事はWSのプログラムを作り、参加者に美術館に来てもらって参加してもらうという形態ですか?
WSに限らず、教育普及活動全般のディレクションをして、来場者または山口という地域にとってのYCAMとはどんなものなのか?を考えていました。
会田さんの「教育普及」観を聞かせて下さい。
かつて全国の美術館では、「教育普及」を翻訳とか通訳という言い方をするところが多かったように思います。作品と鑑賞者の間に立ち、難解な作品についてわかりやすい言葉で解説することを「教育普及」と呼ぶことが多かったんですけれども、よくよく考えてみればすごくネガティブな話というか、二重の意味で失礼で。まずひとつはアーティストの表現力がないということを暗に言っていると思うんですよね。つまりアーティストがやることはわけがわかんないと。もうひとつは、お客さんというのは見る能力がないということを暗に言っている。
そういうネガティブなことに修正パッチを当てるような仕事を設定し、それを「教育普及」って呼ぶのはよくないなと思ったんです。
まず大切なのは作品と鑑賞者をダイレクトにつなげることであり、その際に重要なのはいかに作品を観るか?という「批評」ということなのだと思いました。
批評ですか。
YCAMでは委嘱作品が多く作られていて、そこで生まれる新作っていうのは、言わば生まれたばかりの山じゃないですか。その頂上に登りたいけれどもルートがわからない。良くできた作品批評というのは、例えば富士山のようにメジャーな作品だと、すでに専門家によるルートは探索されていて、こういうふうに登るんだよというのが完成している。それを「充分にこなれた批評」と捉えるならば、一方で新作の場合、登山道という批評を自分で作らなきゃいけないので、山に登ると同時にルートを探索するようなことになるわけです。でも、そこでは他人がつけた足跡を辿っていくのとは異なった楽しみがあるわけです。えもいわれぬアートの体験に対し、自分なりに言葉を与えて捉え直し、他の鑑賞者と共有していく。作品を作るアーティストだけが創造的なのではなく、鑑賞をしていく行為そのものにも創造性は潜んでいる、ということを伝える。そういったことを後押しできるような「教育普及」はありだなと思いましたね。
具体的な例をお話します。「映画を2回観る会」(YCAM/2012年~)という企画をやってきたんですけれども、20分とか30分ぐらいのショートフィルムを1回見て、そのあと、鑑賞者全員にインタビューをして回って、何が見えたか、どういう印象だったかなどを言ってもらいます。そのあとにちょっと司会者が多少の情報を・・・いつ作られた映画とか・・・そういうことを少しだけ伝えて、もう1回同じ映画を観るという、全部で2時間ぐらいのプログラムです。
面白いのは映画というのは複製芸術なので、1回目の上映と2回目の上映で作品自体は変わらない。まったく同じものが上映される。でも作品の見え方は凄く変わるんです。そこではすなわち何が変わったというと、鑑賞者自身が変わったということなんですね。
作品を見るっていう経験は、「自分が変わる」ということが含まれている。
同じ映画を見ても違うように見えたりとか・・・子供の時に見ていた絵本を、大人になって見返してみると、「ああ、こんなメッセージがあったんだ」とびっくりするというような。
そういう経験というのがあるんだということを知ってもらうだけでも「教育普及」の価値はあると思うんですよね。
「作品を見せてわかりやすい言葉で解説して納得して帰ってもらう」ことよりも、作品を見る間にいろんな言葉を聞き、自分で何かを表明してみるみたいなことをして、すぐに納得が行かないかもしれないけれど、自分の立ち位置やビューポイントがどんどん増えていくということが、いかに大事かということをわかってもらうことが「教育普及」では重要だと思いました。

アウトリーチなどはあまり行わなかったのですか?
実はアウトリーチであれば何でもよい、とは思っていなくて。
これは、とあるアーティストが言っていたのですが『学校側は、受け入れ方としてアーティストをお客さんとして呼んで、授業の代替えで何かやってもらって、最後は先生が生徒を整列させて、生徒に「アーティストの方に皆でお礼を言いましょう!」というようなことをやっている。学校という場において、お礼やお辞儀をすることは重要だけれども、そういった社会の固定化した枠組みからズレようとしているアーティストの主義主張はどうなるんだろう。学校の関係者ではない人がその場所に行く意味はなんだろうか?』と。そういうアーティスト側の意図も含めて複層的に考える必要があります。アウトリーチさえしておけばいいとか、いろいろな報告書にアウトリーチに何箇所行きましたというようなことが、アリバイ的に書かれていくこと自体に疑問がありました。
同時に、地方の都市にあるYCAMという出来たばかりのメディアアートセンターが、どういうふうにブランディングできるかということを考えると、オリジナルで何かを作り出すということがすごく重要だと考えました。そのオリジナルなプログラムが、一定の汎用性を持ったもので、価値あるものであること、それがありとあらゆる場所で応用されるということを実践しようと思いました。
YCAMが開館して3年か4年ぐらい経った頃だと記憶しているんですが、「教育普及」で作ったプログラムが、ベネッセコーポレーションの設立50周年のイベントで招聘されました。
そういうふうに外の施設やインスティテューションみたいなところから声が掛かって、実施して価値が生まれたということを山口市に逆輸入していくというやり方が、市民に対してYCAMがどういう価値を持っているかを説得していくのには、早いやりかたなんじゃないかと思いましたね。
最初の頃は、市役所などに対してはなかなか説得材料にならなくて、市民の税金を預かって運営しているのに、なぜ市民に対してプログラムを行なわずに、それ以外の地域に対して行うんだということを言われたりしましたね。たしかに、「市」という単位で見ればその通りですが、もっと広い視野を持つと答えが違ってくる。長州人の気質は、広い枠組みも同時に考えられる度量なんじゃないかと思います。
この10年の間にWSプログラムや教育普及活動が、たとえば「キッズ・デザイン賞」の大賞(経済産業大臣賞)に選ばれたり、「文化庁メディア芸術祭」で受賞したり、「グッドデザイン賞」を戴いたりして、外部から評価をもらうという活動を地道にやってきたことで、山口市のYCAMが県外に対してどんな価値を生み出しているのかを、徐々に市民に説明できるようになってきた感じですね。
年間どれくらいの量のプログラムを生み出していくのですか?
ワークショップとして作り出すのは多くなくて、年1本ぐらいです。
すでに出来上がってるWSプログラムに関しては、実施しながら何度も改良していきます。
WSをつくる際には、どういった発想で作られるのですか?
展覧会の企画に付随したWSを作ることもあります。
例として「パスタ建築ワークショップ」というものを紹介します。
これはもともと「コーポラ・インサイト」という作品の展覧会に関連するWSだったんです。
※展覧会「コーポラ・インサイト」(YCAM/2007年10月13日-2008年1月13日)
http://re-marks.ycam.jp/2007/corpora-in-sighte/
※YCAM教育普及展覧会「glitch GROUNDーパスタ建築」
http://re-marks.ycam.jp/2007/pasta-architecture/
(※サイト内の画像を参照)これは写真の上に絵を描いてるんですが、非常に抽象的な概念を用いた作品なんです。コンピューター上のシュミレーションで、風が吹いたりとか光が当たったりとか人がざわめいたりという状態を、環境に埋め込んであるセンサーで集積して、このエリアがどんな状況であるかということを把握し、そのデータに基づいて建物の形状が変化していくという・・・そういう作品なんです。
この展覧会の関連イベントとして開催された「パスタ建築」WSでは、パスタを使って円周状に並べた机の上にそれぞれ建築物を作っていきます。ところが参加者は5分ごとに隣の机にぐるぐると移動しなければならないんです。作品は移動しないので、隣の作品を改良していくという作業になります。改良していくときに、それぞれカードが渡されていて「大きくする」とか「強くする」とか「美しくする」という指示が書かれてあり、それに基づいて作るんです。参加者ごとに、たとえば「大きくする」というオーダーだけを、それぞれの作品に行なっていきます。
これは、セル・オートマトンというコンピュータ科学の問題をシュミレーションするWSになっています。例えるならば、コンピュータの中にエージェントと呼ばれる仮想の生き物を作って、ひとつひとつのセルと言われている小部屋の中で各エージェントがどういう条件でどういうふうに発展していくかということを、ルールを変えながら試しているものなんです。ライフゲームとか人工生命みたいなことにすごく近い分野ですね。
こういった概念が自然界で見いだせるとすると、サンゴの形状やシロアリの蟻塚です。蟻塚はすごく複雑な形をしているんですが、設計者というものがいないんです。シロアリ自体にはシンプルな命令だけあって、目の前のものをこういうふうにしろということしか分かっていないと思うのですが、すごく集積すると、複数のエージェントがいることで総合的に蟻塚が出来上がっていくんですね。
こういうことって面白いと思うんです。たくさんのシンプルな指示だけで複雑で巨大なものが出来上がっていく。パスタ建築のWSも最終的にいろんな形の建築物が出来上がっていくわけです。WSを行ったあとに、展覧会「コーポラ・インサイト」を見ると、「あ、これは自分がやったことと同じだ!」と納得してもらえるんです。何もせずにいきなり展覧会を見たときに、大人はどういう理由で目の前の作品が作られているのか、どんな理屈で出来ているのか一瞬戸惑うことも多いのですが、このWSを経ると、自分がやったことと展示作品がすぐに繋がります。
ただ、展覧会に連動したWSを行うときに、できれば単体のWSとしても自立できる強度を持たせたい。なので、もうひとつ抽象的なレベルでセル・オートマトンの問題を考えた上で、それと齟齬がないような形で、WSをデザインしていく。そうするとコンピュータ科学の中のセル・オートマトンを理解したり、個人の才能に拠らない集合的な知恵というものを理解するためのWSとして、自立したWSになるんですね。
なるほど。
こういうふうにテーマがまずあって、その面白いテーマというものをどういうふうに体験的に学べるかという発想からWSのデザインはスタートするという感じですね。
展覧会に付随する場合もあれば、はじめから独立のWSとしてパッケージされることもあります。
確かに、これを学校にいきなり持っていくと説明するのがとても大変ですね。
そうですね。学校だと授業の科目という問題があるので、これは図工なのか算数なのか理科なのかということで、学校の先生が困るんですね。僕らからするとどっちでもいいと思うんですが、先生からしたらそれはとても重要なことです。学校に持って行く時には、文部科学省の教育指導要領をよく読んで、この部分に当てはまりそうだということを持っていくといいんですが、学校の中にはセル・オートマトンの問題を扱う単元はないので、これは学校では扱いませんというのが普通の理屈ですよね。
固定ページ: 1 2
![]()










