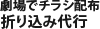![]()
制作ニュース
- インタビューシリーズ:TALK 〜田幡裕亮さん〜
-
15.05/13
限られた世界のようでいて、実はさまざまな職種・活動が存在する舞台業界。そこに関わる多様な人々にスポットをあて、お話を伺うインタビューシリーズ『TALK』。語られる言葉(意思)を通じて、読者の方々にご自身の活動への新しい発見やヒントを感じていただきたい、そんな思いで取り組みます。

教育普及の担当に就いて8年目。インタビューを受けるなど、現場から一歩外に出ていくような仕事も増えてきた。「丸7年なりの経験を伝える必要が出てきているのかも」。普段は主に、世田谷区内の小中学校を巡回する演劇ワークショップ(以下WS)『かなりゴキゲンなワークショップ巡回団』などを担当する。
高校3年間は演劇部に所属したが、公演づくりの型に沿って「決まった役割に人をはめ込んでいくような」演劇のつくり方に違和感を拭えなかった。「あんな人やこんな人が集まった、さて何しよう!ってところから始めたい」。大学入学後、子どもを対象としたWSの進行役アシスタントや、ボランティアスタッフとして児童館に行ったりする中で、そのイメージに近い“遊び”を演劇WSに見出し、卒業後すぐに現職に就いた。
担当する『かなりゴキゲンなワークショップ巡回団』は、先生の希望を伺いながらのオーダーメイド・プログラムだが、事前に先生から聞いた事柄だけで、進行役が行うWSの内容を決めるているわけではない。「子供を見て先生も見て、クラス内の関係性や保護者、周辺地域の様子など、関わってくる色んなものを見て、ようやく見えてくるものがあるように思うんです」。現場で時間をかけないと分からない、そう感じる日々だ。
「いつも同じことしてる?って言われたりすることもあるんですけど」と苦笑しつつ、「公演においてキャストや客層、演出家が毎回異なるのと同じように、学校での演劇WSも、クラスは全部違うし生徒も違うし、進行役も違う。毎回違うんです」と語る。広義の演劇という意味では、(教育普及事業として)演劇WSをコーディネートするのも、公演を制作するのも、それほど違いはないと感じている。
世田谷パブリックシアターは今年で開館18周年だが、子ども達のみならず学校の先生でさえ、WSを通じて初めて劇場の名前や活動を知ることが多いという。「劇場の内外に関わらず、集まった人で演劇(を活用)する場所を『みんなの劇場』とすることが、今の私の仕事だと考えています」。今日も田幡さんは世田谷区内を駆け廻る。(編集部:芳山徹)

1985年、埼玉県出身。
「5月17日(日)には、実方裕二さん(脳性まひによる身体・言語障害を持ちながらもケーキの路上販売・カフェ経営を行っている)との漫才コンビ『ゆーじーず』で、路上演劇祭Japan2015に出演します!」。
【合わせて読みたい!】
◇ 【特集:レポート】学校は「演劇ワークショップ」をどう活用するのか?世田谷パブリックシアターの事例から
![]()